あさのあつこによる青春小説。
高校が舞台で女子が主人公、というこれまで読んできた作品と共通した土台はあっても、中身は少し毛色が違う。
心ないうわさ話、気になる人との出会い、愛する者との別れ、誰しもが青春時代に経験した思い出と同じように、主人公と彼女を取り巻く人たちに拡がるドラマ。
主人公のこころの声には、多感な年代の複雑な心境が詰まっている。
言葉でも眼差しでも想いでも同じだ。どこか曖昧にぼかした方がいい。まっすぐに一途にひたむきに、他人に向けてしまうと痛い。自分で自分を傷つけることになる。
言葉も眼差しも想いも、同じまっすぐさで受け止めてもらえることは稀有なのだ。受け止めきれないものを人は重荷と呼んだり、厄介に感じたり、戸惑いの因としてしまう。そして、受け止めてもらえなかったとき、人は傷つくじゃないか。
好きだった。恋人と二人、肩を並べ、洋祐はどんな季節、どんな風景の中を歩いたのだろう好きだった。過去形の持つ切なさは、誰かを失って初めて理解できる。甘くも美しくない。ただ残酷なだけの切なさだ。
そして、恐らくは作者に十代を主人公にする小説を書かせている最大の理由を、主人公に語らせている。
十代って残酷な時間なんだ。
十八歳の今、つくづくと思ってしまう。
とても、残酷な年代なのだと。
否応なく全てが変わっていく。変わらされてしまう。留まることは許されず、立ち止まることも許されない。ただ前へ、前へ、先へ、先へと進むだけだ。急流に浮かぶ小舟みたいだ。
十代ほど、たくさんの人に出会い、たくさんの人と別れる時代はない気がする。出会いと別れを繰り返す時代、「さようなら」そんな別離の挨拶とともに、二度と会えなくなる人たち。その人たちをいつの間にか忘れていくわたし、忘れられていくわたし。出会いも別れも生々しく、儚い。
残酷な年代だ。
二度とは戻れないあの日々と、経験しようのない女の子の気持ちを追体験できる一冊。

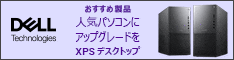



![[800字コラム] 需要と供給](http://n-mizuno.com/wp-content/uploads/2017/03/nokia-150x150.jpg)
![[nmbooks] ルワンダ中央銀行総裁日記](http://n-mizuno.com/wp-content/uploads/2017/03/tgv-cafeteria-150x150.jpg)

