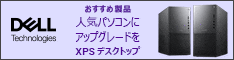1992年、26歳の若さで急逝したロック歌手、尾崎豊の姿を追う筆者。
尾崎に向かって「きみ」と語りかけて進められる文体には、ベ平連出身とは思えない、左翼の人にありがちな感情むき出しな筆致とは無縁の、しっとりとした説得力を帯びている。
講談社
売り上げランキング: 288993
ただ、本書において昭和天皇の戦争責任論を持ち出して尾崎とその時代を語ろうとするのはいささか無理があるというか、本書の書かれた1993年(平成4年)の時点では、戦争を巡る先帝の内面を証す研究も資料も今ほどは多くなかったのではあるのだが、左翼の人にありがちな思考回路の跳躍が見て取れてしまうのは、本書が1980年代の浮き足だった世相と尾崎自身とを丁寧に描写しているだけに、やや勿体ない気がするのだが。
尾崎の死の伏線となる多くの出来事について、土砂降りのようになされた多くの報道の本当のところ、と思しき事実関係が克明に綴られる。例えば、尾崎が個人事務所「アイソトープ」を設立した経緯について、僕が以前読んだ週刊誌の記事には、息子の商品価値に気づいた家族が、その利益を独占するために設えたといった論調が見られた。が、実際には尾崎が信頼できる知人たち支援者たちを、自らの言動のせいでひとりまたひとり失っていった結果、自分の家にしか帰るところがなかったのではないか、と本書からは読み取れる。
今日では幻冬舎の社長として知られる見城徹が、『月刊カドカワ』の編集長として接した尾崎評は、なかなか興味深い。
「他者が見えないんだな、と思った。他者のない人だと。ぼくはその後、彼とはかなり深いつきあいをすることになったんだけど、これは最後まで変わらない印象だったな。コンサートでも書くのでも、彼は、『みんなを愛している』とか、『きみたちのために歌いたい』とか言うでしょ。しかし、あれは本気じゃないのかもしれない。要するに、作りごとなんですよ。みんなのことなんか頭のなかになくて、自分しかない。そう考えれば、わかりやすい。だから、他者に対する遠慮がないだけに、表現者としてみれば、おもしろい表現もいっぱいできたんですよ」
そして、本書では明確に表現されてはいないが、その死に至る迄の尾崎の奇怪な言動、猜疑心の塊のようになってしまった姿、急速に冒されていった肝臓と食欲の減退… といった事象には、どうしても覚醒剤の匂いがついて回る。即ち、逮捕後も尾崎はクスリに頼り、溺れていたのではないか。
10代の教祖と祭り上げられた尾崎を、どうして周囲の誰もが本気で理解し、支え、守ってやれなかったのだろうか、と本書を読み終えてつくづく思ってしまう。
ファンならずとも読んでみたい一冊。