オウム事件に触発された筆者が一晩で書き上げ、パソコン通信上で発表した文書が基になった鋭い考察。
オウムを語ることは結局自分を語ることになってしまうという筆者は、自身の「グル」との邂逅や「出家」(家出)を通じて、麻原に惹かれていった信者たちの心境を抉ってゆく。
不用意に世代論をふりかざすのは危険だと思うが、同時に「世代」という言葉でしかくくれないものがあるのも確かだろう。上祐、青山、村井といった幹部の顔をテレビで見て、おれは妙な感覚に襲われた。彼らと自分との差がよくわからなかったからだ。
人類滅亡は全然怖くなかったが、滅亡以前に、自分だけが病気か事故で死んでしまうのは嫌だった。余談だが、もう少し後になって、個人的な死の恐怖をごまかす理屈をおれは発明した。あくまでゴマカシではあるけれど、こういうものだ。つまりガンや交通事故の死亡率が何パーセントかは知らないが、そんなものは人間の死亡率に比べればものの数ではないということである。人間の死亡率は100パーセント。何をやっても、どんな立派なやつでも人は必ず死ぬ。死んだ後は、きれいさっぱり何にもない。なにもハルマゲドンを待たずしても、人間は「死」に関しては生まれながらに平等だということ。こう考えると、愉快な気持ちにならないか。
さて、もう一度「オウム真理教は狂気だ」という麻原の論法に戻ってみよう。この発言は、実は二重の意味で巧妙なのである。ここには自己言及(ひらきなおり)で相手の質問を封じると同時に、究極の問い掛けが含まれているからだ。
「では、あなたがたが暮らしているそちらの世界はまともなのか」
「狂っていない、といい切れる自信があるのか」
これが、あの発言に秘められた問いである。おれたちは、知らず知らずこれを答えるはめに陥ってしまうのだ。
おれは、おれが「まともである」ことを、どうやって証明すればいいのだ?
頭がよくて真面目なやつほど、これは難問だろうと思う。いい大学を卒業して、いい会社に入って、いい結婚をして、出世するのが「まとも」な生き方なのだろうか。たしかにまともかもしれないが、それがはたして幸せといえるのか。
考えれば考えるほど「まとも」がわからなくなってくる。ふと前を見ると、麻原尊師がニッコリ微笑んでいる。さあ、入信まではあと一歩だ。
要するに、おれは「ここではないどこか」に連れて行ってくれるのだったら、誰でもよかったのだ。(中略)考えてみれば、おれがXに惹きつけられたのも、家を出るきっかけが欲しかったに過ぎなかったのだろう。おれは、実家や学校での生活が嫌でたまらなかったし、退屈な人生の予感に最初からうんざりしていた。そうしてXと出会ったわけだが、しばらくして気がついたら、おれはXに精神的に従属する関係になっていただけだった。要するに、何にも変わっちゃいなかったのだ。
「人間は生まれながらにして自由だ」っていうのは、ヒッピーの基本的な信仰だよね。でも、そこから出発すると、それを阻むものすべてが敵になるわけ。敵が国家だったり、学校であったり、親であったり、ズルい大人であったり。対立関係で考えると自由ってものがさ、相対的なものになって矮小化されるわけ。結局は、その自由を阻むものに対して乞食のように振る舞って、おこぼれを貰う状態になってしまう。(中略)ていうことはだよ。ちゃんと考えてゆくとね。自由を阻むものは現実社会そのものに他ならなくなっちゃうよね。となるとだよ。「人間は生まれながらにして自由だ」っていうのが、ファンタジーの世界の話になっちゃうわけ。それで、その幻想が確保できる場所が逃げ場になっちゃうわけ。
単行本、文庫とも既に絶版になっているのが何とも惜しい名作。

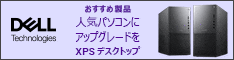




![[800字コラム] それ以前の問題](http://n-mizuno.com/wp-content/uploads/2017/03/nokia-150x150.jpg)
