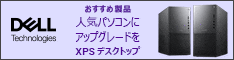「偉大な兄弟(Big Brother)」が支配する薄暗いロンドンの街。市民の活動は常にテレスクリーンと呼ばれる監視装置によって見張られていて、反政府的言動をした者はいつの間にか姿を消している。
早川書房
売り上げランキング: 4486
1984年のある日、政府官庁でひたすら過去の新聞記事の改竄を手がけている主人公ウィンストンはある日、思い立って禁止されている日記をつけ始め常に間違いを犯さない「偉大な兄弟」の支配する世界への疑問を日々膨らませてゆく。
「おしまいに党は2足す2は5だと発表するようになるだろうし、自分もそれを信じなければならなくなるであろう。遅かれ早かれそうした主張が行われるのは避けがたいことであった。彼らの置かれている立場の論理的な必然性がそれを要求するのだ。ただ単に経験の正当性でなく、客観的な事実の存在そのものまで、党の哲学によって暗黙のうちに否定されるのである。異端の中の異端こそ常識だった。そして戦慄すべきことは正反対の考え方をしたために殺されるということではなくて、むしろ彼らの方が正しいかも知れぬと思いこむことであった。」
そして、やはりご法度の恋愛に陥ったウィンストンに秘密警察の捜査の手が伸びていく。肉体的、精神的に徹底して行われる拷問の末に、主人公が見たものは……。
「党はただ権力のために権力を求めている。われわれは他人の幸福などにいささかなりとも関心は抱いていない。われわれは権力にしか関心がないのだ。富のためでも贅沢のためでも、また長生きするためでも幸福を求めるためでもない。ただ権力、それも純然たる権力のためなのだ。純然たる権力とは何か、それはこれから説明する。(中略)およそこの世に、権力を放棄する心算で権力を獲得する者はいないと思う。権力はひとつの手段ではない、れっきとした一つの目的なのだ。何も革命を守るために独裁制を確立する者はいない。独裁制を確立するためにこそ革命を起こすものなのだ。迫害の目的は迫害それ自体にある。権力の目的は権力それ自体にある。拷問の目的は拷問それ自体にある。さあ、これで私のいわんとするところが分かりかけたかね?」
全体主義国家の行き着く先を克明に描いたSF小説だが、批判者を失った組織が、その規模の大小に関わらず陥っていく一つの構図を暗示しているとも言えると思う。即ち、独裁者ひとりの思考、意見だけが尊ばれ、一人一人の考え方や個性といったものが丁寧に排斥されてゆき、その状態を「皆が団結した素晴らしい組織」と言って憚らない集団は、我々の身近なところにも存在しているかもしれないということ。
読み方によって多様な示唆や教訓が得られる不朽の名作。