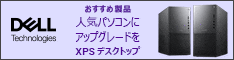1985年の日航ジャンボ機墜落事故。これほど僕に衝撃を与えた出来事はない。
この年の暮れに祖父を亡くすまで、死を身近なこととして感じていなかったし、憧れのジャンボ機が無残な姿を晒し、当たり前の日常が一瞬にして瓦解して、人間の無力さを見せつけられた驚きは、今でも消えていない。いや、消えていないどころか、社会人になって、飛行機に多く乗るようになってから、自分があの日の乗客になる悪夢に時々うなされる。
この本に出会ったのは中学校の図書館で、事故からは数年が経っていたが、初めて読んだ時に当時のことがまざまざと思い返されると同時に、筆者の筆力に圧倒されて、ノン・フィクションに傾倒するきっかけになった。
ダッチロールという流行語をつくったいわゆる「落合証言」について、本書で当の本人である落合由美さんがその内容の一部をあっさり否定してみせ、ダッチロールなる言葉は知らなかったとまで言い切っていることが非常に興味深い。
本書が輝く最大の理由のひとつは、事故原因や技術的な解説にページを割くのではなく、あくまでもこの惨事に対峙する人間を主人公に置き、かつ筆者が自らの感情を極力抑えていることにある。
<ビッグ・ビジネス・シャトル>のなかでは、乗客のだれも仕事のことを書き残さなかった。だれひとり、仲間や上司や部下にあてた遺書やメモを残さなかった。文章が発見されたかぎりでは、そうである。いきなり死に直面したとき、乗客たちがとっさに書いた文章の内容は、死にたくない、というぎりぎりの言葉と、家族にあてた愛と惜別の言葉だった。それしか、なかった。そうだったのだとすれば、空港ロビーにあふれるあの新しさのざわめきと、軽く高揚した気分とは何なのだろう。陰影のない明るさと、高度なテクノロジー・システムのただなかにいることの気配。その雰囲気と、ビジネス分野の先端で、きびしい競争をつづけることの緊張感とは、たぶん波長があっている。遺書に残された言葉は、その背後で、新しさや、先端にあることや、競争に夢中になることの、あやうさと儚さを語っているように、私には感じられた。そんなものをきどるよりも、ずっと大切なことがある、と。もちろん、それは、だれもが自覚していることに違いない。競争に追われ、小さな勝利に満足し、ささいな敗北にがっかりする、そんな日常のくり返しのうさんくささは、だれもが気づいている。しかし、気づいていながら、表層を飾り、きどってふるまい、関係のなかの孤独を耐えることのほかに、どんな日々の暮らし方があるのか?
中学生の頃には分かるようでよく分からなかったこの一節は、歳を取った今、生きることの意味、生きることの本質を僕に問い返し続けている。
単に航空機事故のドキュメントとしてでなく、人生について深く考えさせられもする一冊である。本書の迫力を経験した後では、山崎豊子の『沈まぬ太陽』は所詮はつくりもの、という印象を今でも拭いきれていない。
(おまけ) そのほか、日航ジャンボ機墜落事故関連で読んでおきたい本: